戸籍を超えた家系図作成、家系調査、先祖調査を専門としています。
TEL. 047-723-6845
月‐金.9〜17時、外出中は留守電にお願いします
お寺と神社のお参りの違いThe difference of Buddhist Temple and Shinto Shrine
先祖調査では、お寺と神社の訪問は欠かせません。
そこで、お参りについて、それぞれの違いなどをまとめます。
1. お寺と神社の違い
| お寺 | 神社 |
| 山門をくぐる時は、一礼してからくぐる。入門する気持ち。朱色に塗った門は格式が高い。 | 鳥居は一礼してからくぐる。 |
| 参道を歩くのはどこでも良い。(仏教の教え、中道。バランス重視) | 参道は端を歩く。正面は神様の通り道。どちらかと言うと左側がよい。 |
| 参道に出ている屋台やお店は、参拝後。食欲は後に満たす。 | 手水舎(てみずや)で身を清める。手と口を清める。左手→右手→口→左手→ひしゃくのえ。ひしゃく一杯の水ですべて行う。 |
| 常香炉(じょうこうろ)で煙をかぶるのは、体を清めるため。 | 拝殿は鈴を鳴らしてからお参りをする。お賽銭はいくらでも良い。 |
| 境内では撮影して良い。 | 神社は真正面から撮影してはいけない。 |
| お賽銭は、お金を捨てる修行である。断捨離も同様。喜捨(きしゃ)という。 | お賽銭は前回のお願い事の対価。「賽」はお返しという意味がある。 |
| 合掌は、手を合わせて礼をする。 | 拝殿のお辞儀の角度は90度。手は少しずらして合わせる。 |
| 自分だけではなく他者の幸福も祈る。 | お願いは、感謝の言葉+名前+住所を念じる。 |
2. お寺と神社、その他知っておきたい事
| お寺 | 神社 |
| 仏像の写真をスマ歩の待ち受けにしても御利益にはならない。 | 絵馬にイラストや絵は描いてもよい。昔は本物の馬を奉納していた。絵馬として名称だけが残った。 |
| 授与所での御朱印をインターネットで買っても御利益はない。行った行為に御利益がある。 | 引いた後のおみくじは持って帰るのがよい。おみくじはそもそも神様のお告げの言葉であった。 |
| 露出の多い服装はNG。お寺は修行する場。 | お札は高さは目の位置より高い所で南向きか東向き。熊手は神棚か玄関に置く。 |
| お守りはいくつ持ってもよい。 | |
| お守りはおおむね1年間でお返しする。買った神社に返すのが基本。 | |
| 伏見稲荷神社は惣本宮。全国からのお礼があり鳥居がたくさんになった。一つくぐる毎により神聖な領域になる。 | |
| 普段から地元の神社(氏神様)に行く事。その土地を守ってる神様である。 |
※「お寺と神社お参り検定」(2017年9月テレビ朝日放送)参考
ペg
メディア関係者のみなさまへ

NHK チコちゃんに叱られる!
に出演しました
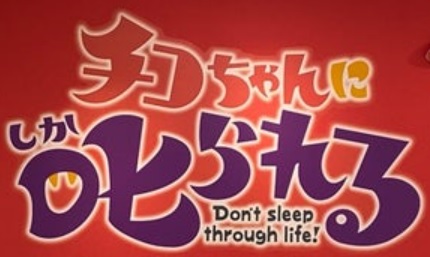

テレビ朝日
『中居正広のキャスターな会』
に情報提供しました
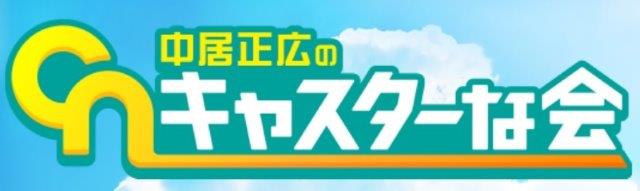
日本テレビ news every.で
電話取材を受けました!
TBS この差って何ですか?で
所蔵文書が使われました!

萩本勝紀の本
ノウハウすべてを公開

↑
クリックで購入
画面に飛びます
国家資格者である行政書士が担当します
調査は国家資格者である行政書士が担当します。行政書士には法律で守秘義務が課せられています。個人の情報は厳守しておりますので、安心してお任せ下さい。

クリック↑願います

代表萩本勝紀
(行政書士・姓氏研究家・保育士)
プロフィールはコチラ
萩本勝紀所蔵文書はコチラ
萩本勝紀のブログ
行政書士萩本勝紀のビジネスブログです。 http://hagimoto-blog.jugem.jp/
http://hagimoto-blog.jugem.jp/
郷土史調査の知恵袋
●知っておくとよい情報、ちょっとした知識、言葉の意味を解説ニュース・情報・コラム
●日本人に多い名字(佐久間ランキング)●お寺と神社のお参りの違い
●萩本勝紀所蔵文書一覧
●所蔵する壬申戸籍(山形県、京都市)
●所蔵する壬申戸籍(広島県、埼玉県)
●NHKのファミリーヒストリーの調査方法を考察する<壇蜜編>
●NHKのファミリーヒストリーの調査方法を考察する<竹中直人編>