戸籍を超えた家系図作成、家系調査、先祖調査を専門としています。
TEL. 047-723-6845
月‐金.9〜17時、外出中は留守電にお願いします
古文書KOMONJYO
先祖調査では古文書や行政文書の調査も行います。
以下は代表的な古文書について説明をしています。
宗門人別改帳
宗門人別改帳とは、江戸時代に作られていた現在の戸籍に近い役割をする台帳です。
宗門改めは、慶長18(1613)年の江戸幕府によるキリスト教の禁教令以後随時行われ、寛永14(1637)年の島原の乱を契機として、幕府で実施されました。
幕府は寛文11(1671)年の条例で、「全ての人は必ずどこかの寺の檀家とならなければならない」として、全国的に宗門改帳を毎年作成するよう命じました。
毎年3月、寺からキリスト教信者でなく仏教徒である証明として、各家ごとに檀那寺の印が押され、領主の役所に提出されました。
これを寺請(てらうけ)の制度といいます。
この宗門人別改帳に名前が載っていないと「無宿人」として、居住等の様々な制限を余儀なくされました。
 |
 |
分限帳
分限帳(ぶんげんちょう・ぶげんちょう)とは、江戸時代、大名の家臣の名前、禄高(ろくだか)、地位、役職などを記した帳面のことです。いわゆる武士の名簿録のようなものです。
 |
検地帳
検地とは、俗に竿入(さおいれ)、縄打(なわうち)ともいわれ、農地の測量調査のことをいいます。
始めて検地が全国的に実施されたのは、豊臣秀吉による“太閤検地”でした。
村内の土地を一筆ずつ、田・畑・屋敷などの区別とその所在、面積および土地の良し悪し(上・中・下・下々)に分けて、作人(検地帳に登録された人で名請という)と収穫量をはかり、これを一村ごとにまとめたのが検地帳(いわば土地台帳です)です。
その土地の石高に対する納税義務と引き換えに、その土地の所有権が保証されました。
 |
 |
旧土地台帳
古文書という部類のものではありませんが、家系調査では必要になるため挙げています。
旧土地台帳とは、明治22年頃から昭和12年頃まで利用された、土地の所有者を登録するための台帳です。ご先祖様が土地を所有していたのか借りていたのかが分かります。字名も記載されています。
 |
 |
過去帳
これも古文書という部類のものではありませんが、家系調査では必須ですので挙げています。亡くなった人の戒名(または法名・法号)、俗名、死亡年月日、享年(行年)などを書いたものです。寺院が所有・管理している過去帳と、各個人が所有・管理している過去帳があります。
 |
過去帳に関しては、萩本勝紀のビジネスブログもご参照ください。
→ 過去帳は部外者に見せないで」というニュースに対して
→ お寺の過去帳について
萩本勝紀所蔵文書
私 萩本勝紀は、いくつか古文書を所蔵しています。私の家系図作成・先祖調査講座の際、受講生にお見せしています。
 |
五人組御改帳(慶応3年) 宗門人別帳(文政4年) 検地帳(寛永4年ほか) 武艦(安政5年) ほかに検地野帳(明和8年)があります。 |
※五人組とは
五人組とは、古代の五保(ごほ、五戸で一保とした)の制にならった庶民の隣保組織をいいます。
江戸幕府の五人組の起源は、慶長2(1597)年、豊臣秀吉の士卒を対象とした五人組や十人組に始まるといわれています。江戸幕府成立以後、農民や町民の組織に広まっていきました。
五人組という制度は、村の中で向こう三軒両隣を一般的に一組とし、五軒で相互にお互いに助け合い、年貢米を連帯責任で申し付け、納付するものです。
また、子どもの間引きや遺児の禁止、キリシタンの禁止など、お互いに生活の様子を監視させて、隠し事や悪事を働いている者を密告させるなど、治安維持にも役立てました。
なお、五人組といっても必ずしも五人(戸)ではなく、四人組や六人組、七人組など一組の構成は村によって異なりました。
五人組の長を、組頭(くみがしら)、判頭(はんがしら)などと呼んでいました。
 |
 |
※武艦とは
武艦とは、大名や江戸幕府役人の氏名・石高・俸給・家紋などを記した年鑑です。武家の当主の氏名・官位・家紋・石高・役職・内室・城地・格式・幕府への献上品・行列の指物・用人などがこと細かく記されています。
 |
 |
壬申戸籍
明治5年式戸籍(いわゆる壬申戸籍)を所蔵しています。
壬申戸籍の説明は こちら をご覧ください。
 |
分限帳
松本藩水野家の分限帳(享保期)を所蔵しています。
ペg
メディア関係者のみなさまへ

NHK チコちゃんに叱られる!
に出演しました
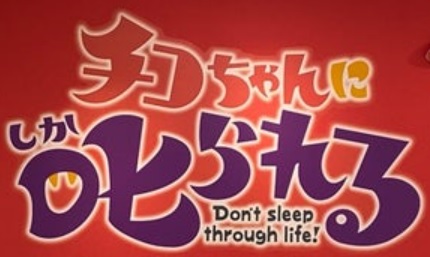

テレビ朝日
『中居正広のキャスターな会』
に情報提供しました
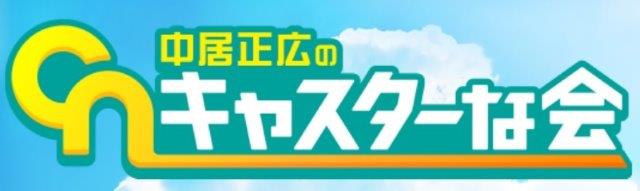
日本テレビ news every.で
電話取材を受けました!
TBS この差って何ですか?で
所蔵文書が使われました!

萩本勝紀の本
ノウハウすべてを公開

↑
クリックで購入
画面に飛びます
国家資格者である行政書士が担当します
調査は国家資格者である行政書士が担当します。行政書士には法律で守秘義務が課せられています。個人の情報は厳守しておりますので、安心してお任せ下さい。

クリック↑願います

代表萩本勝紀
(行政書士・姓氏研究家・保育士)
プロフィールはコチラ
萩本勝紀所蔵文書はコチラ
萩本勝紀のブログ
行政書士萩本勝紀のビジネスブログです。 http://hagimoto-blog.jugem.jp/
http://hagimoto-blog.jugem.jp/
郷土史調査の知恵袋
●知っておくとよい情報、ちょっとした知識、言葉の意味を解説ニュース・情報・コラム
●日本人に多い名字(佐久間ランキング)●お寺と神社のお参りの違い
●萩本勝紀所蔵文書一覧
●所蔵する壬申戸籍(山形県、京都市)
●所蔵する壬申戸籍(広島県、埼玉県)
●NHKのファミリーヒストリーの調査方法を考察する<壇蜜編>
●NHKのファミリーヒストリーの調査方法を考察する<竹中直人編>