戸籍を超えた家系図作成、家系調査、先祖調査を専門としています。
TEL. 047-723-6845
月‐金.9〜17時、外出中は留守電にお願いします
名字を知るABOUT LAST NAME
名字の広まり
名字は、平安時代末に発生し、徐々に広まったものです。
その種類の多さは日本の名字の特色です。
研究家である丹羽基二氏がまとめた「日本苗字大辞典」(芳文館発行・平成8年)には、29万1531件もの名字が登録されています。
名字の「名」は領地をあらわします。
名字の「字」は土地の小区分のことです。
つまり、「名字」とは「領地の地名」といった意味になります。
武士は土着したその土地の名、つまり「名字」を名乗りだしました。
名字は総領(本家)から総領(本家)へと伝えられましたが、多くの家では、分家筋は総領(本家)の名前を名乗れませんでした。
というのも、総領は本家の権威を守るため、分家に同じ名字を許さなかったからです。
同じ名字が増えると、どの家が本家か分からなくなってしまうのもひとつの理由です。
本家と分家で名字や家紋を“引き継ぐ・引き継がない”といった契約を結ぶ家もあったようです。
そこで分家は、本家から与えられた土地を開墾し、自らの領地としてその地名を、新たな自分の名字としてつけていったのです。
このような名乗りの名字が、いつしか姓氏と同じように使われるようになっていきました。
名字と苗字の違い
名字が次々と生まれたのは室町時代までと言われます。
というのも、新しい開拓農地が新しい名字を生み出すためには開発できる土地が必要です。
しかし、戦国時代も後期になると全国に封建制度が行きわたり、新たに開墾してその地名を名字とするような場所はなくなりました。
さらに江戸時代になると土地は大名のものであり、勝手に開墾、所有することは出来ません。
つまり武士たちは名字の地にすべき土地を所有できなくなってしまったのです。
こうなると名字は単に祖先から伝わる家名でしかなくなります。
そこで、江戸時代になると名字に代わって「苗字」という文字が用いられるようになりました。なぜなら名字は、もはや“領地の地名”ではなくなったからです。
“苗”には、「同じものから派生した」という意味があります。
つまり先祖を同じくする同種の集まり、ということを意味します。
幕府の出した法令もすべて“苗字”が使われ、意図的に“名字”は使わなくなりました。
幕府は「苗字・帯刀」を武士の象徴として、苗字の“公称”を禁止し、百姓・町人はこれを使えませんでした。
実際には、公でなければ目をつぶって見ぬふりをすることもありました。
庶民は苗字を持っていなかったのではなく、公の場で名乗れなかっただけです。
現地調査で各地を訪ねると、江戸時代でも、神社の氏子台帳、寄付台帳、建築の奉加帳、棟木、村の私文書の連名などには苗字が書かれています。
明治の名字
明治政府は、明治3(1870)年「今後、平民に苗字の使用を許す」という平民苗字許可令を布告しました。
しかし苗字の届出がはかばかしくなかったため、明治4年には「戸籍法」を発令して苗字の登録を促しました。これが全国的な戸籍であり「壬申戸籍」と呼ばれるものです。
さらに明治5年には、すでに登録済みの苗字の変更を禁止しました。
江戸時代、変名は当たり前でしたから。
通称と実名の並記も禁止しました。
名前の変更例
(苗字) (通称) (実名)
吉田 市右衛門 則数 → 吉田則数
石谷 備後守 清昌 → 石谷清昌
以下のような官位が名前に取り入られて通称となった「左衛門」「右衛門」「兵衛」(通称)などは廃れていきました。
官位から名前に取り入れられた通称の例

名字のつけ方
苗字の登録を促しても、なお苗字を届け出ない者がいるので、明治8年には「平民もかならず苗字を称し、不詳の者は新たにつけるべし」と布告しました。つまり命令となったのです。これを「平民名字必称義務令」といいます。
このとき、新たに名字をつけた人は、おおむね次のような付け方をしたと言われています。
・屋号をそのまま苗字とした(高田屋→高田、塩屋→塩谷など)
・土地の名前を入れた
・名主や庄屋につけてもらった
・名士や名主から一文字譲ってもらった
・山、川、木などの自然から連想してつけた
(山のふもと→山本、栗の木がある→栗本、その周りに住む→栗林・栗田など)
・語呂を組み合わせた
・思いつきでつけた
代々伝わってきた名字や屋号、明治になって始めてつけた名字・・・
名字にはご先祖さまのそのときの想いが反映されているといえます。
あなたの名字にはどのような意味があるのでしょう。
ペg
メディア関係者のみなさまへ

NHK チコちゃんに叱られる!
に出演しました
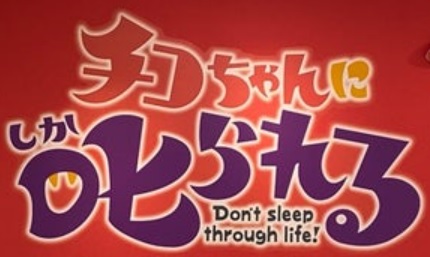

テレビ朝日
『中居正広のキャスターな会』
に情報提供しました
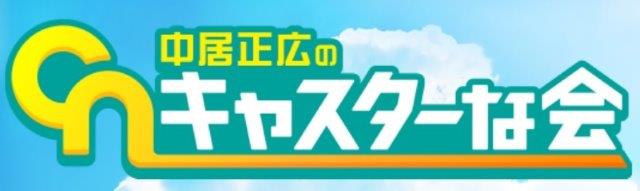
日本テレビ news every.で
電話取材を受けました!
TBS この差って何ですか?で
所蔵文書が使われました!

萩本勝紀の本
ノウハウすべてを公開

↑
クリックで購入
画面に飛びます
国家資格者である行政書士が担当します
調査は国家資格者である行政書士が担当します。行政書士には法律で守秘義務が課せられています。個人の情報は厳守しておりますので、安心してお任せ下さい。

クリック↑願います

代表萩本勝紀
(行政書士・姓氏研究家・保育士)
プロフィールはコチラ
萩本勝紀所蔵文書はコチラ
萩本勝紀のブログ
行政書士萩本勝紀のビジネスブログです。 http://hagimoto-blog.jugem.jp/
http://hagimoto-blog.jugem.jp/
郷土史調査の知恵袋
●知っておくとよい情報、ちょっとした知識、言葉の意味を解説ニュース・情報・コラム
●日本人に多い名字(佐久間ランキング)●お寺と神社のお参りの違い
●萩本勝紀所蔵文書一覧
●所蔵する壬申戸籍(山形県、京都市)
●所蔵する壬申戸籍(広島県、埼玉県)
●NHKのファミリーヒストリーの調査方法を考察する<壇蜜編>
●NHKのファミリーヒストリーの調査方法を考察する<竹中直人編>